機能物性研究グループ
機能物性研究グループは、生体現象や、化学反応、駆動された量子物質とナノデバイス等において実現する多彩な非平衡多体現象について俯瞰的な立場から研究を進めることで、その隠れた学理と未知の機能を解き明かし、応用に資することを目的とする。近年、光遺伝学や細胞内物性計測、励起状態や非平衡状態の時間分解測定、ナノスケールの分析・分光測定などの実験法が飛躍的に進歩し、同時に、計算・データ科学による理論解析や、揺らぎの定理やフロッケ・エンジニアリングなど非平衡統計力学の構築が進展している。これら重点的な研究課題に関連した物性研究所の研究者数名がコアメンバーとなり、さらに数名の所員が従来の部門に属しつつ併任として参加する。
| メンバー(*は部門主任) | 主な研究内容 | |
|---|---|---|
 |
秋山 英文 教授 研究室HP |
|
 |
井上 圭一* 准教授 研究室HP |
|
 |
岡 隆史 教授 研究室HP |
|
 |
杉野 修 教授 研究室HP |
|
 |
林 久美子 教授 研究室HP |
|
| 所内兼務のメンバー | |||
|---|---|---|---|
 |
野口 博司 准教授 研究室HP 本務は附属物質設計評価施設 |
 |
原田 慈久 教授 研究室HP 本務は附属極限コヒーレント光科学研究センター |
 |
松田 巌 教授 研究室HP 本務は附属極限コヒーレント光科学研究センター |
 |
眞弓 皓一 准教授 研究室HP 本務は附属中性子科学研究施設 |
 |
森 初果 教授 研究室HP 本務は凝縮系物性研究部門 |
 |
吉信 淳 教授 研究室HP 本務はナノスケール物性研究部門 |
 |
リップマー ミック 教授 研究室HP 本務はナノスケール物性研究部門 |
||
| 客員メンバー | |||
|---|---|---|---|
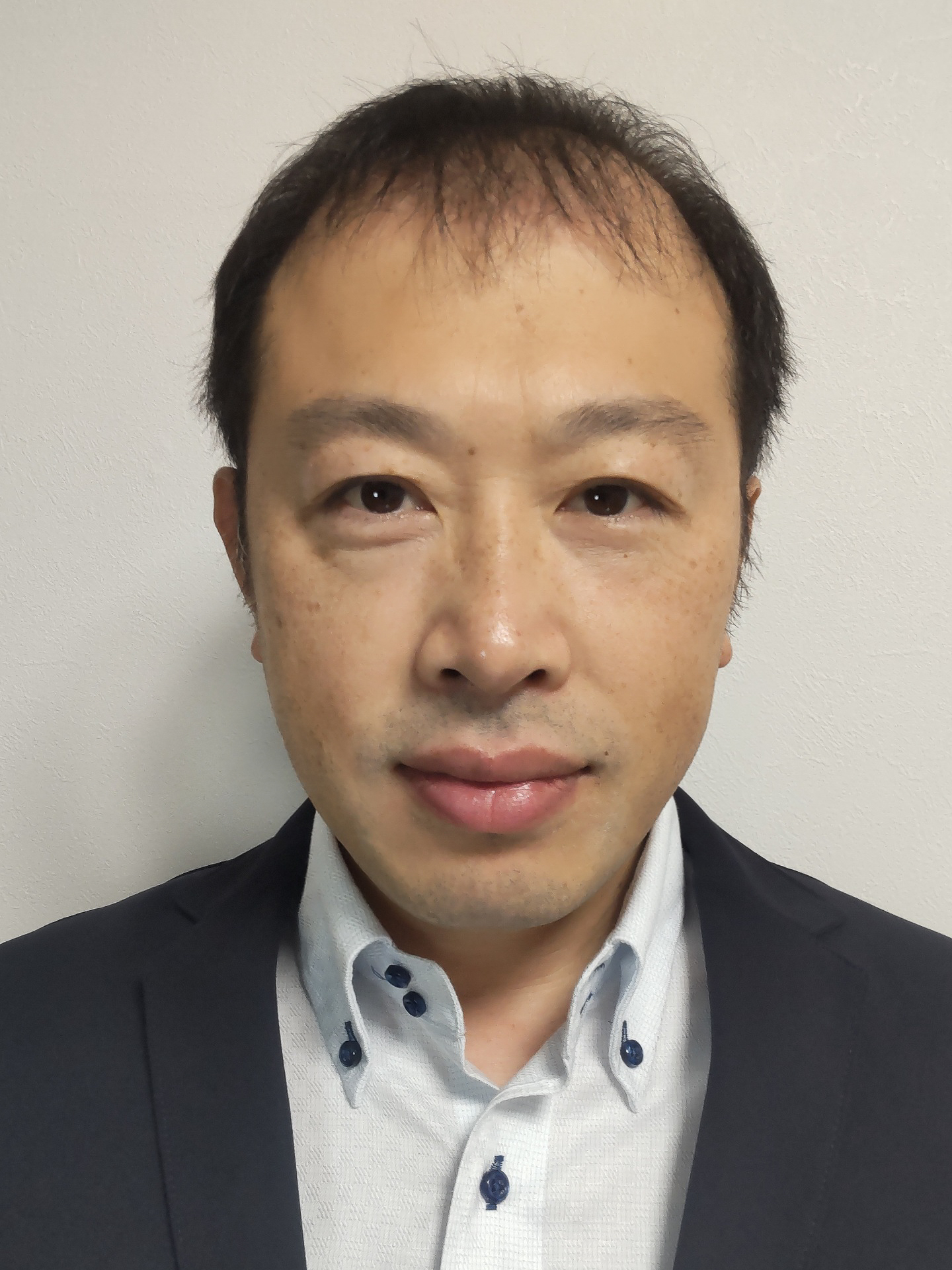 |
小布施 秀明 客員准教授 |  |
ジャーン ティエンティエン 外国人客員教授 |
