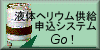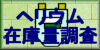液体ヘリウム 利用案内
物性研以外の部局の場合、液体ヘリウムの生産能力の問題から、事前に部局間での了承が必要となります。
詳細については液化室までお問い合わせ下さい。
※「新領域創成科学研究科」「IPMU」については部局間の了承済みです。
液体ヘリウムの供給申込方法
液体ヘリウムの供給申し込みは、下記の「液体ヘリウム供給申込システム」より行ってください。
システムに関して質問、不具合等ありましたら液化室までご連絡下さい。
新規に利用される方は、以下を良くお読みのうえ、各種登録等を行ってください。
登録が完了次第、システムの利用が可能となります。
液体ヘリウムを使用する際の義務
物性研究所低温液化室が供給する液体ヘリウムを使用する場合には以下のことが最低限の義務となります。これらは効率よく、かつ少しでも回収率を上げ、安くて使用しやすい寒剤を供給するために必要なことですので、ご理解の上、ご協力お願いします。
- 「液体ヘリウム使用者登録」「液体ヘリウム使用装置登録」の申請
■ 申請用紙はこちら→http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/download/download.html - ヘリウムガスを回収できない場合は、液化室からは供給できません。外部より液体ヘリウムを購入して利用して下さい。
- 使用する全てのヘリウム回収口に、液化室指定の逆止弁及び流量計を設置すること。
- 実験装置などは、確実に回収配管につなぎ、全てのヘリウムガスを回収すること。特に、自然蒸発分は大気に逃げるような構造になっているものは、これらの装置も改良して、必ず自然蒸発分も回収すること。
■ 装置の改良の詳細はこちら→http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/returntec/returntec.html - 毎月、ヘリウム在庫量を報告すること。在庫量調査日は毎月第一月曜日(その日が休みの場合は翌日、もしくは翌週の月曜日)となりますので必ずその日のうちにご提出願います。報告は原則として、毎月配布される紙の「LHe在庫量調査願い」に記入して提出するか下記のwebページから行って下さい。その際、研究室のユーザーコードが必要となりますのでご注意下さい。
- ヘリウム容器の持出・返却の際には、必ず所定の手続きを踏むこと。無断で持ち出した場合には、ペナルティを課せられる場合があります。
- 返却する液体ヘリウム容器には、必ず液体ヘリウムを容積の10%以上残すこと。また、やむを得ず残量が10%以下になってしまった場合は必ず液化室員にその旨報告すること。無断で返却した場合には、容器が常温になっている場合には従来通り容器の所属に関わらず予冷を行って貰うほか、ペナルティーを課せられる場合があります。
- 物性研究所の寒剤を新たに使用する全ての人は、必ず液化室指定の講習を受けること。例年春に行われる「高圧ガス保安教育(新人教育講習会)」がそれにあたります。
■ 講習会の詳細はこちら→http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/lecture/index.html
供給までの流れ(新規利用者向け)
供給までに必要な手続き等の大まかな流れは以下のようになります。 登録は新たに使用する場合に必要となります。通常は登録が完了すれば、「供給申込」 「容器の持ち出し・返却」のサイクルとなります。
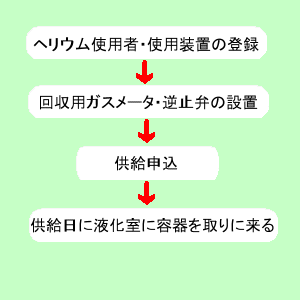
容器 |
共有化※1 |
供給待ち時間 |
汲み置きのためほとんどなし※2 |
供給量の算出 |
容器番号のバーコードを読み込み、重量をロードセルにて計測しパソコンにて自動算出※3 |
供給可能日時 |
土日祝・液化室員不在時を除く全日 |
※1 都合により容器を共通化できず、固有の容器を使用するユーザーは供給日の調整をすることがあります。
※2 従来は供給が終わるまで、最低でも1、2時間ほど待たなければなりませんでした。新体制では、容器を共通化するため汲み置きが可能になり、容器の交換とパソコンに必要事項を入力する時間しかかりません。
また、汲み置き方式のため必ず容器内にヘリウムを容量の10%程度残す必要があります。容器を常温にした場合には、従来通り容器の所属に関わらず研究室にて予冷を行って貰います。
※3 供給量が自動算出になるので、容器重量等のデータが変わってしまうと正しく計測できません。
容器の改造(ヘッド部分のスウェジロックをゴム栓に変更する等)は行わずに、貸出時の容器形状で必ず返却してください。
具体的な登録方法等について
- 研究室内に、ヘリウムの回収配管があることを確認して下さい。無い場合は研究室負担で配管を行って下さい。
なお、配管工事を行う際は研究所全体に影響が及ぶ恐れがあるので、必ず工事を発注する前に液化室にご連絡下さい。また、回収配管にバルブを割り込ませて新たに配管する等で外部に工事を発注する場合は、発注より2-3ヶ月掛かる事もありますのでお早めに確認を御願いします。 - 研究室内の配管の最上流に回収用ガスメータと逆止弁を設置して下さい。■ 逆止弁・回収用ガスメータの設置方法
- 【物性研究所内】液化室にガスメータと逆止弁を用意してありますので、下記設置法を良く読み、サイズ等を確認してから液化室まで取りに来て下さい。なお、液化室にストックしてある物以外は研究室経費で購入して下さい。
- 【物性研究所外】ガスメーターなどは研究室で用意する事となっています。設置すべきものが不明な場合は液化室までご相談下さい。
- 設置が終わったら必ず液化室のチェックを受けて下さい。
- 平行して、ヘリウム使用者・使用装置の登録を行って下さい。登録用紙はダウンロードのページからダウンロードして使用するか、もしくは液化室においてありますので取りに来てください。
- 登録は常時(土、日、祝日除く9:00~17:00)受け付けておりますので、登録用紙に必要事項を記入の上、液化室に直接お越し下さい。
- また、事務手続き上、実際に液体ヘリウムの使用を開始する2日前までに登録の申請を行うようお願いします。
- その他、不明点等ありましたら液化室(内線:63515)までご連絡下さい。
研究室内に回収配管を増設する・既設の回収配管を新たに使い始める場合
- 研究室内に新たに回収配管を増設する場合は研究室負担で配管工事を行って下さい。
なお、配管工事を行う際は研究所全体に影響が及ぶ恐れがあるので、必ず工事を発注する前に液化室にご連絡下さい。 - リザーブ室や以前、他の研究室が使っていたなどの、既設回収配管のある研究室を、新たに使い始める場合は必ず登録を行って下さい。登録方法は上記と同じ手順となります。
- 回収用ガスメータ・逆止弁を設置して下さい。詳細は以下をご覧下さい。
■ 逆止弁・回収用ガスメータの設置方法 - 設置が終わったら必ず液化室のチェックを受けて下さい。
- その他、不明点等ありましたら液化室(内線:63515)までご連絡下さい。
液体ヘリウム容器を新規購入した場合
- 新たに液体ヘリウム容器を購入、移管等した場合には、ヘリウム容器の登録をお願いします。
- ヘリウム容器は容器内の温度が常温の場合、新品で購入した場合でも、液体ヘリウムを供給することが可能になる状態になるまでに2週間前後時間がかかることがあります(真空引き・予冷が必要な場合がある)ので、登録はお早めにお願いします。
- 液体ヘリウム容器の専用登録用紙はないので、液体窒素容器の登録用紙を使用してください。
- 供給できる液体ヘリウム容器は液化室のトランスファーチューブの形状に合うものとなりますので、液体ヘリウム容器を購入する際にはご相談ください。
- その他、不明点等ありましたら液化室(内線:63515)までご連絡下さい。
- 容器は基本的に共用をお願いしていますが、研究室の都合で専用とする場合にはその旨を必ずご連絡ください。
液体ヘリウム容器について
液体ヘリウムの容器はその性質上、あまり丈夫では無い作りとなっています。また、容器の真空が悪くなった場合には、再排気などにかかる時間は最短で2週間程度となっています。それらについての情報を掲載しています。
■ 詳細はこちらをご覧下さい。
注意点・その他
- 容器台数に限りがあるので、1つの研究室で容器を多数または長期にもたれると供給に支障を起こす可能性があります。最低必要台数以上は研究室で確保せずに、必ず液化室まで返却してください。
供給を効率化するため、できるだけ容量の大きい容器を使用してください。最近は、250L容器が不足しております。100L容器で利用可能な場合はこちらの利用もご検討いただき、バランスよくご利用下さい。- 研究室サイドに求めるものも多くなりますが、これらは回収率を上げ、安くて使いやすい寒剤を供給するために必要なことですので、ご理解の上ご協力お願いします。
- 液体ヘリウムの供給体制に関してはこちらも参考にしてください。
- その他、質問等ありましたら液化室まで