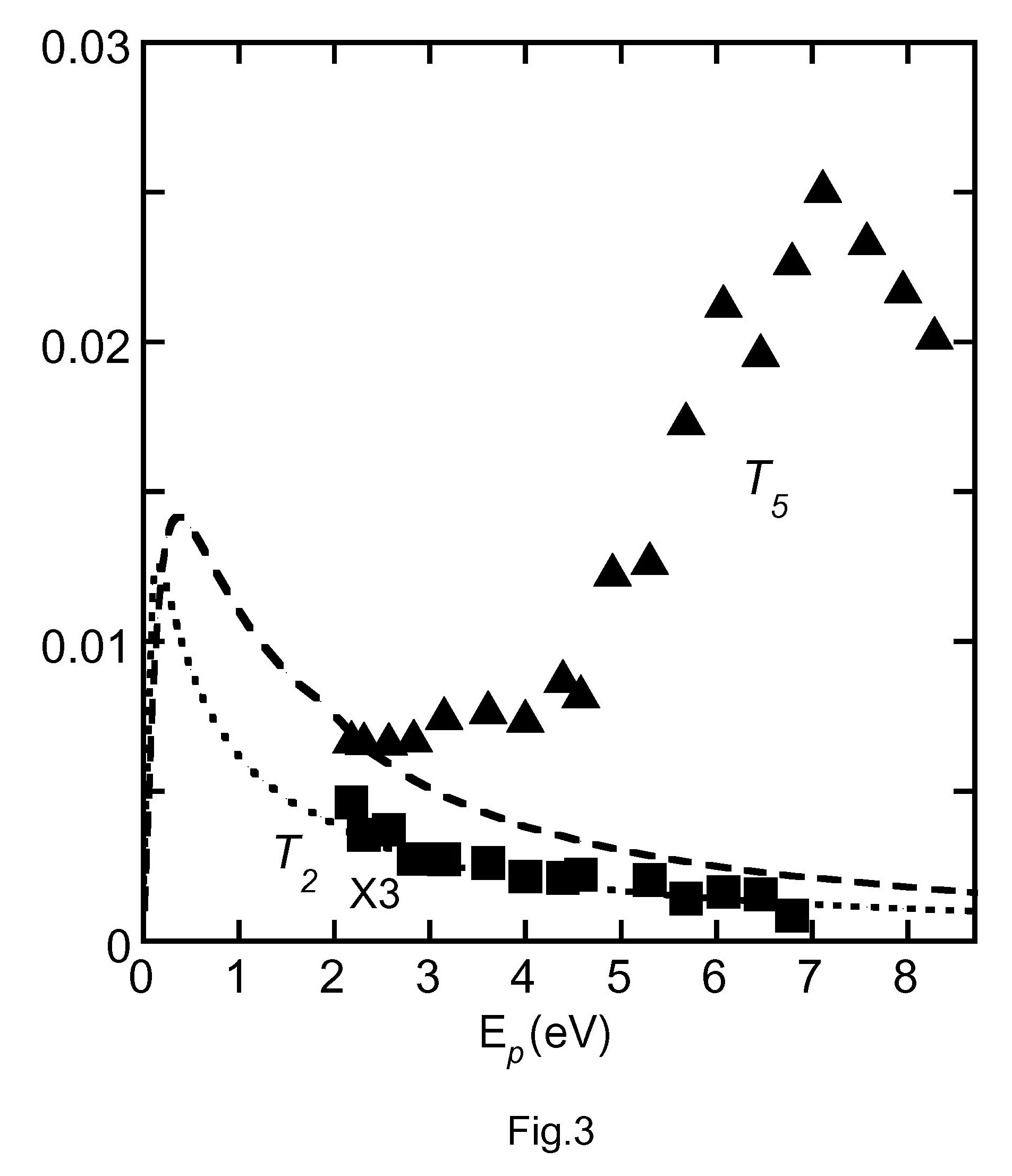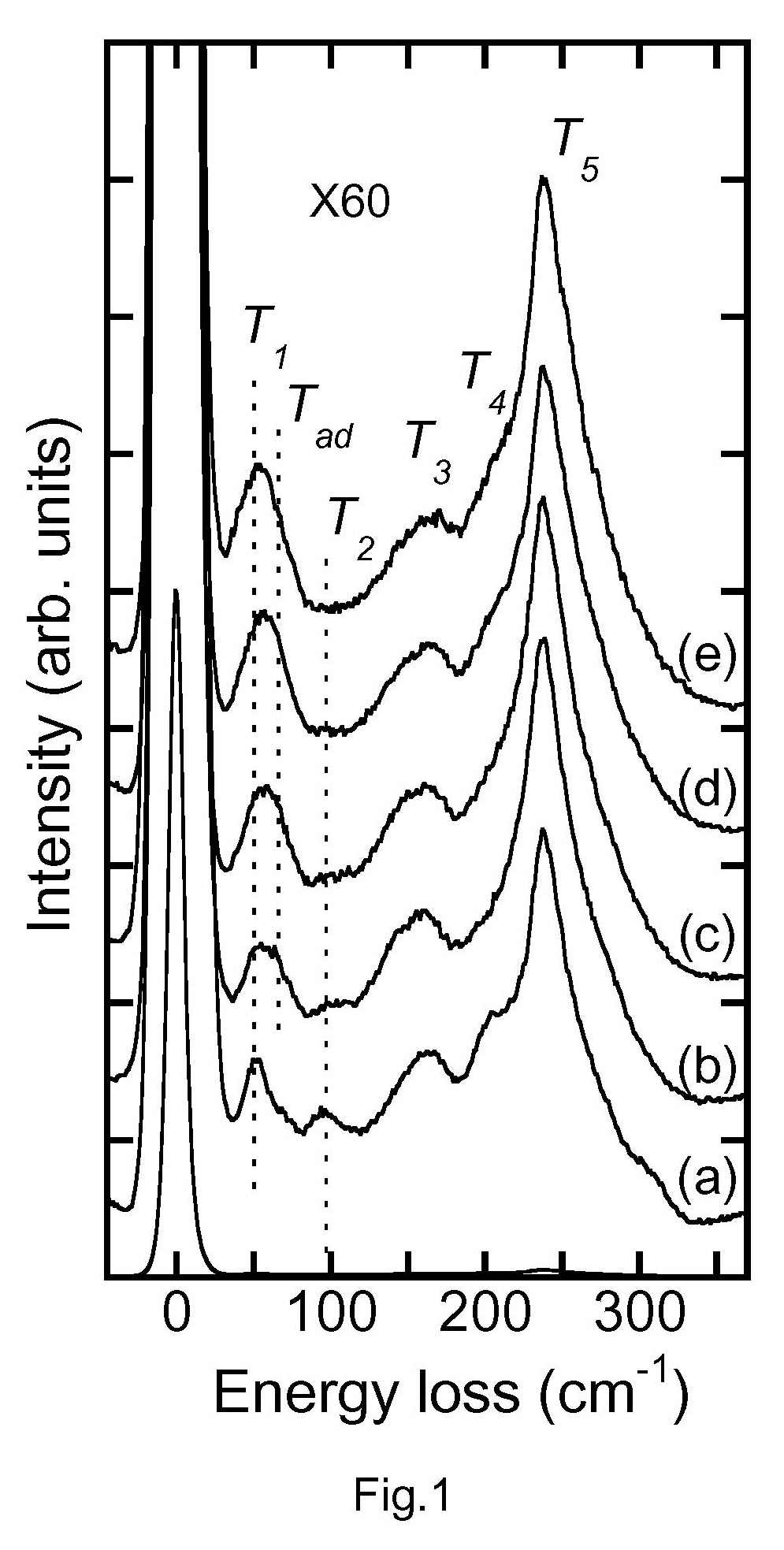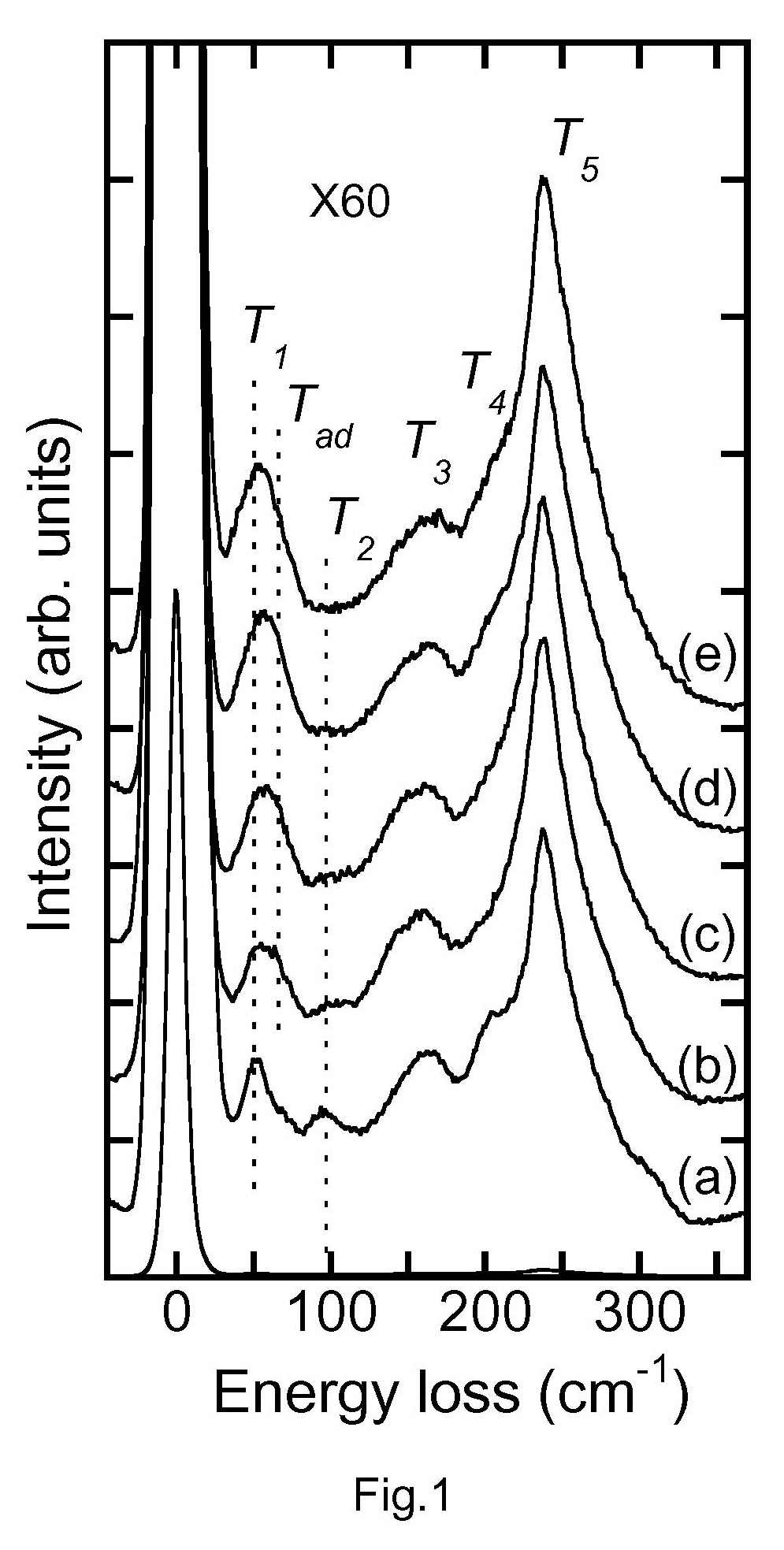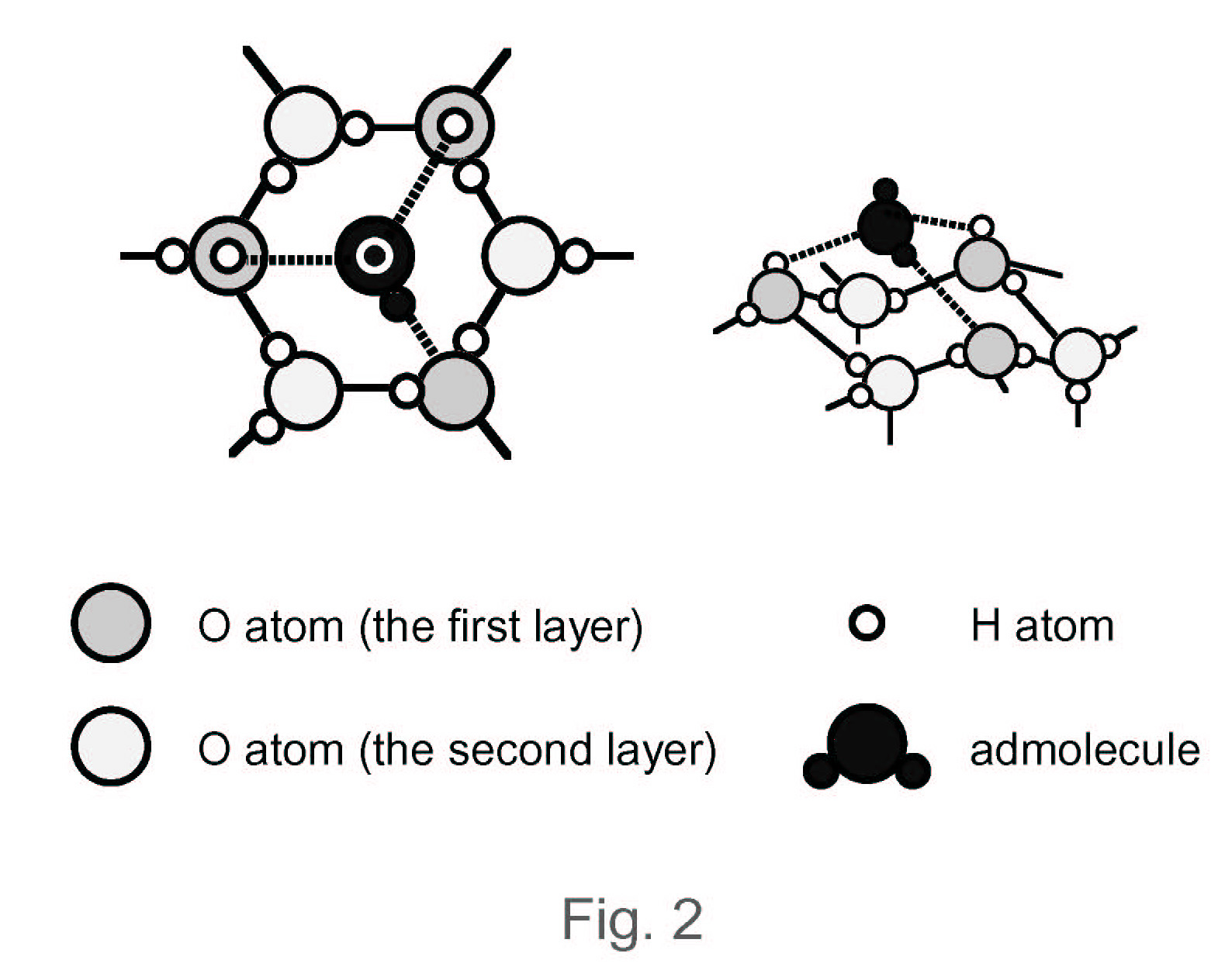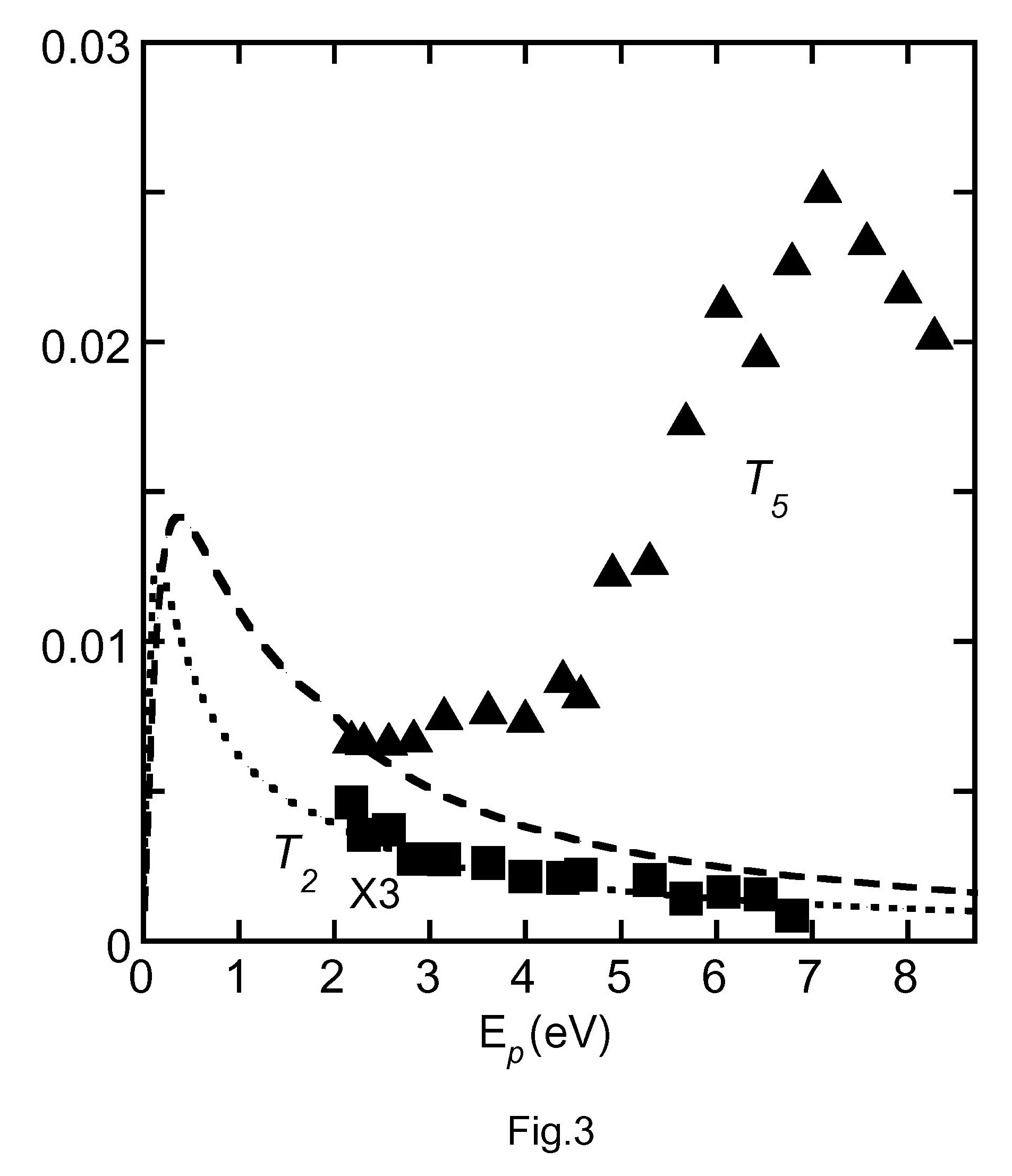研究成果最終報告
「分子凝集体表面の動的
振る舞い」
(京大院理)西嶋光昭・奥山
弘
1.研究
目的と成果の概要
本研究では電子エネルギー損失分
光法(
EELS)を用いて、氷表面の振動状態を全振動エネ
ルギー領域で調べ、表面光学フォノンのソフト化を観測した。また氷表面への分子吸
着のプロトタイプとして水分子の吸着状態について調べ、氷の成長過程における中間
種を観測した。さらに電子と氷の相互作用について調べ、表面とバルクにおける散乱
機構の違いについて考察した。
2.研究
成果
2-1.
氷表面振動モードの観測
結晶性氷薄膜は
Pd(111)表面を基板温度
128Kで気体状水分子に露出して作成した。実験に用いた
結晶性氷薄膜の膜厚は10層程度であり、蒸着量は熱脱離
分光法によって決定した。上記方法で作成した氷表面の全振動領域(30-3000
cm-1)のEELS測定を行
い、束縛並進振動モードによるロスピークを観測した(Fig.1a)。これらのピークの中には、氷表面にさらに少量の水分子を低温
(85 K)で吸着させた場合に強度を失うピークがあること
が確認され(Fig.1b-1e、T2) 面に由来するピークであると同定した。実験で得られたこの表面モー
ドのエネルギー値は、計算により過去に報告されていた氷表面第一層中の水分子の振
動エネルギーと一致し、氷表面光学フォノンモードであると結論づけた。氷表面の水
分子は水素結合による配位数が内部(4配位
)に比較して減少していることが予想され、従ってこの
ようなソフトな表面局在モードが出現すると考えられる。 また束縛回転領域においても同様の実験から470, 665, 825
cm-1に表面固有の振動モードを観測した。分子内振
動(O-H伸縮)については赤外吸収法による振動モード
の研究が進められてきたが、EELSによって新たな情報が
得られた。
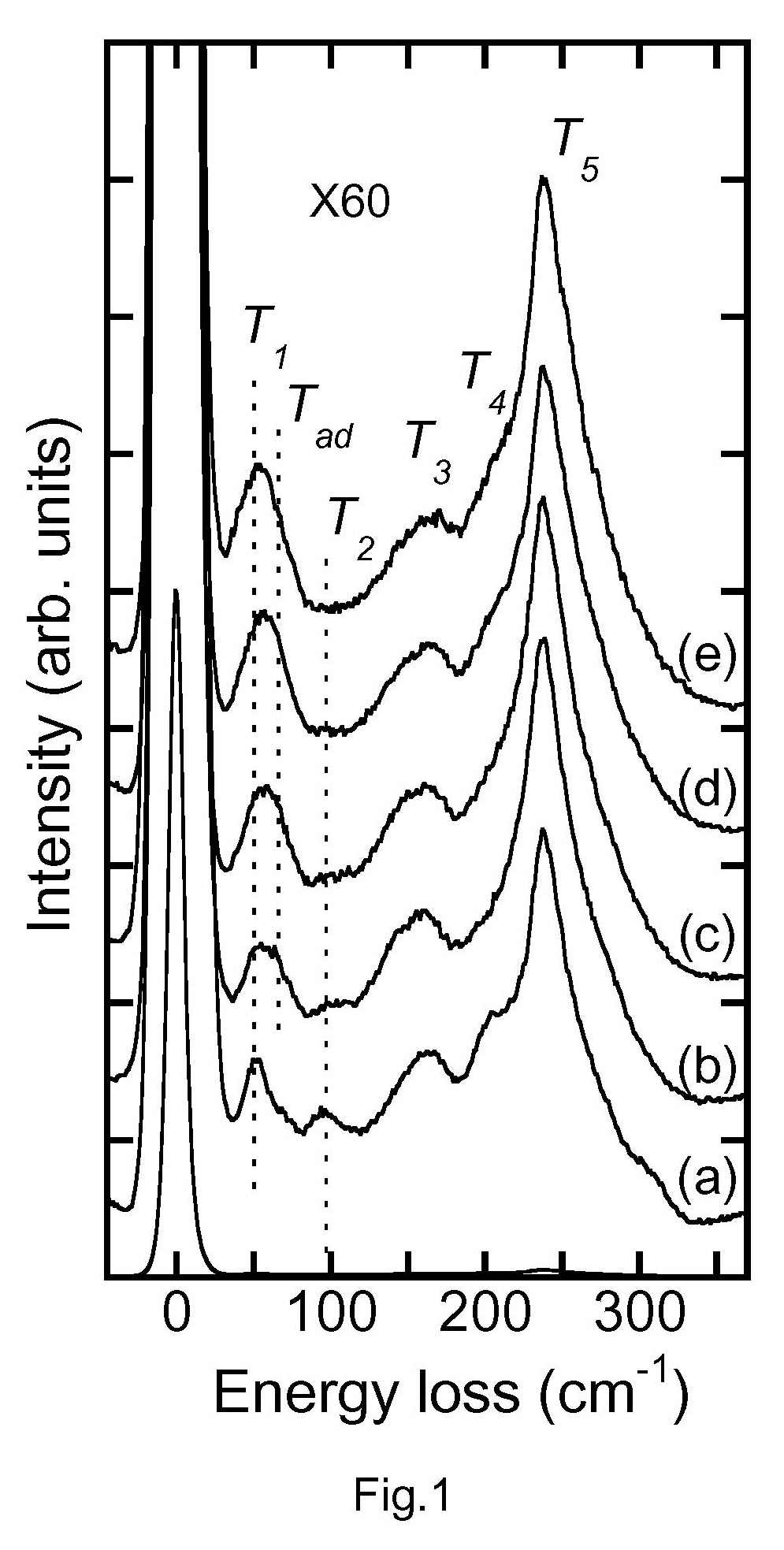
2-2.
氷表面上に吸着した水分子
結晶性氷表面上での水分子吸着を
85Kで行うと表面モードの消滅と同時に吸着水分子によるピークの成長が
確認された (Fig.1b-1e、Tad)
Fig.2は水分子の吸着状態を示しており、本研究ではプロトン
が真空側に向いた状態が優勢であることがわかった。この水分子吸着表面を再加熱
(128K)すると水分子吸着前と同様の結晶性氷表面のスペ
クトルが再現する (Fig. 1a)。再加熱により吸着水分子
が表面拡散を起こし、より安定なバイレイヤー終端表面を再構成することを示唆して
いる。Fig.2の吸着水分子は氷成長過程における準安定
中間種であることがわかった。
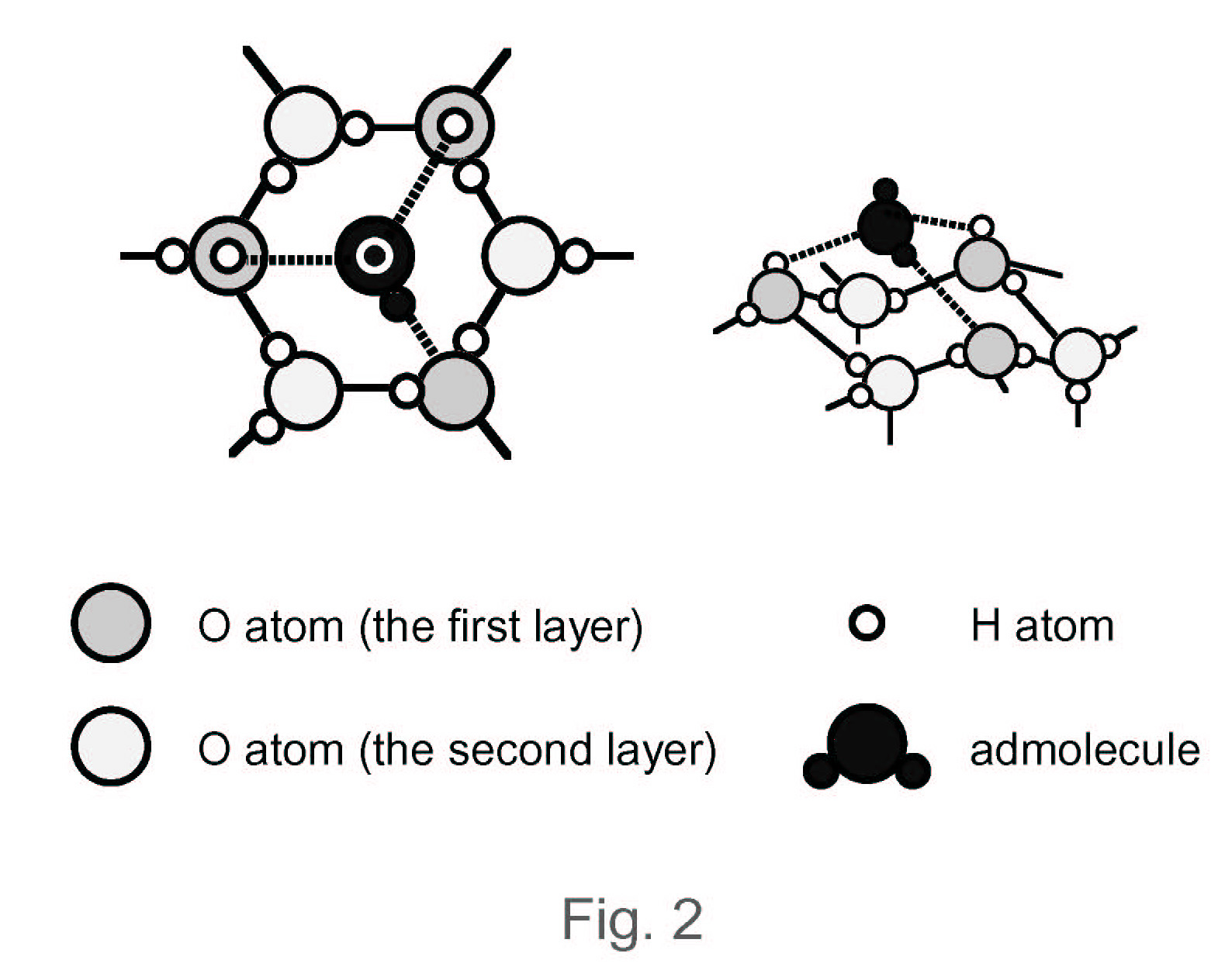
2-3.
氷の電子散乱機構
電子の入射電子エネルギー値
(Ep)を変化させることにより振動強度が変化する。これは入射電子が氷の
空バンドに共鳴することによる。Fig.3はバルクと表面
に由来する振動モードをEpに対してプロットしたもので
ある。表面モード(T2)はEpとともに単調に減少する。これは長距離の双極子散乱機構が優勢であ
ることを示す。一方、バルクモード(T5)は
氷のバンド構造を反映して、7 eV付近で最大値を取る
(共鳴散乱)。すなわち、表面とバルクで電子の散乱機構が異なることがわかった。