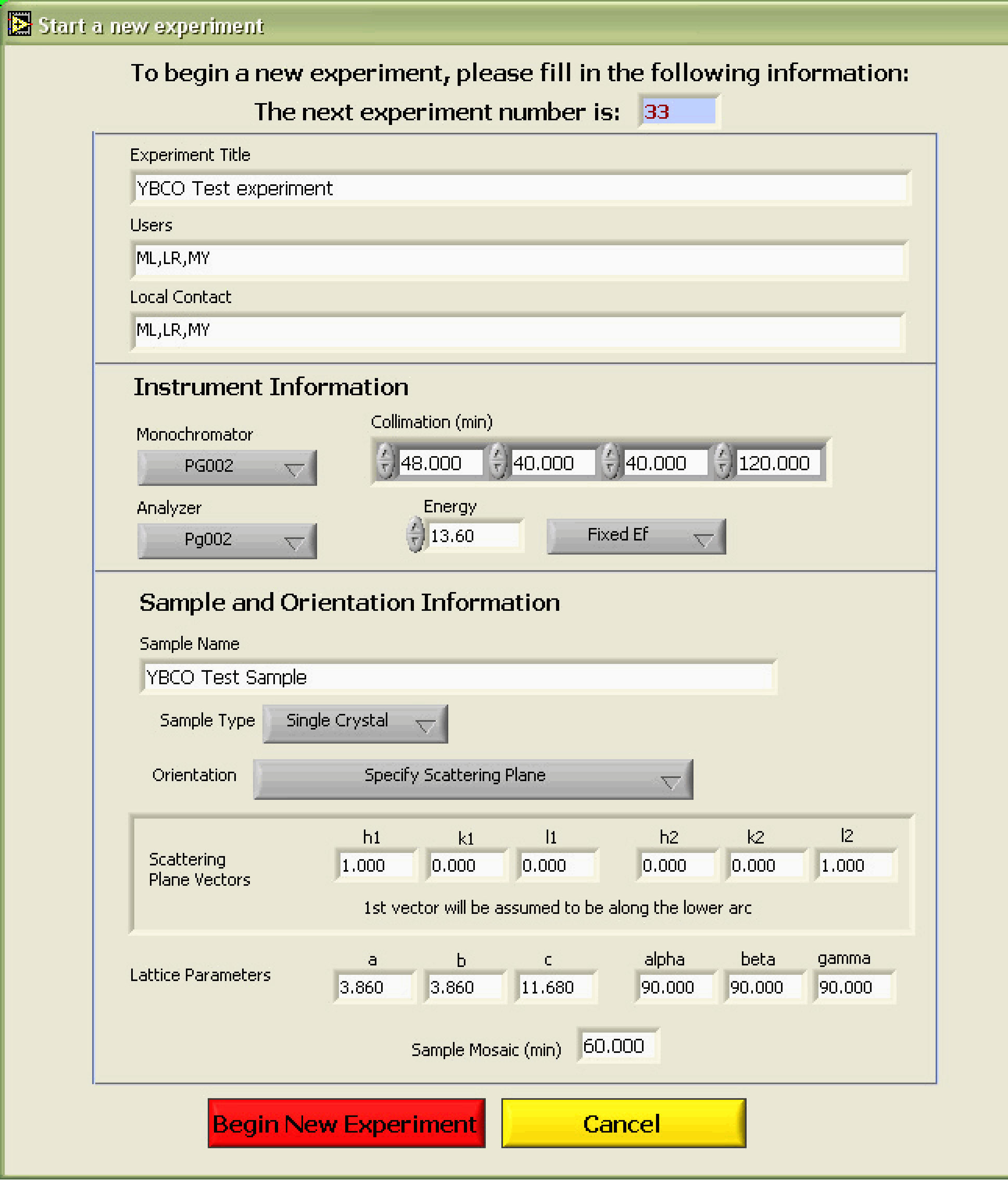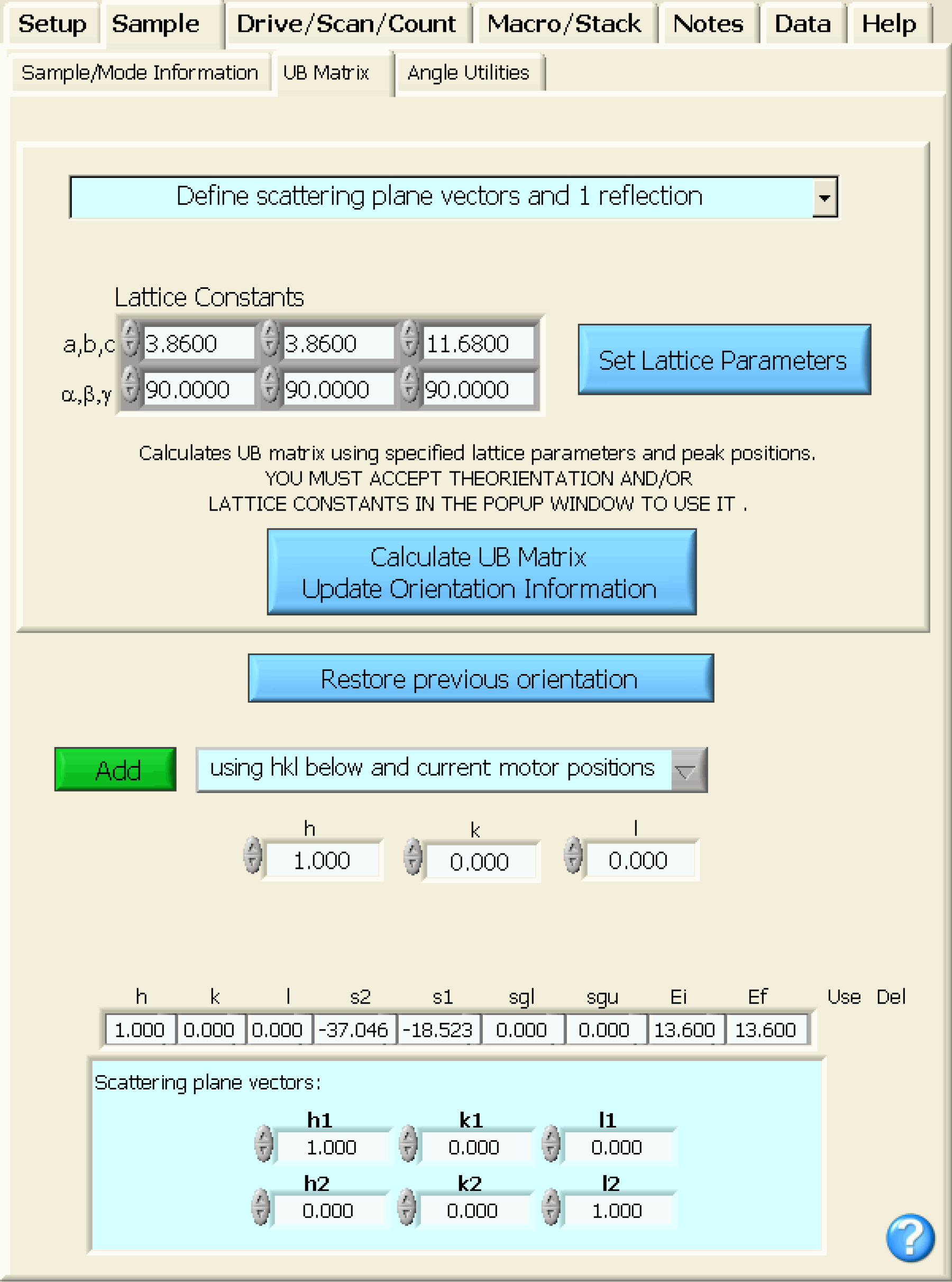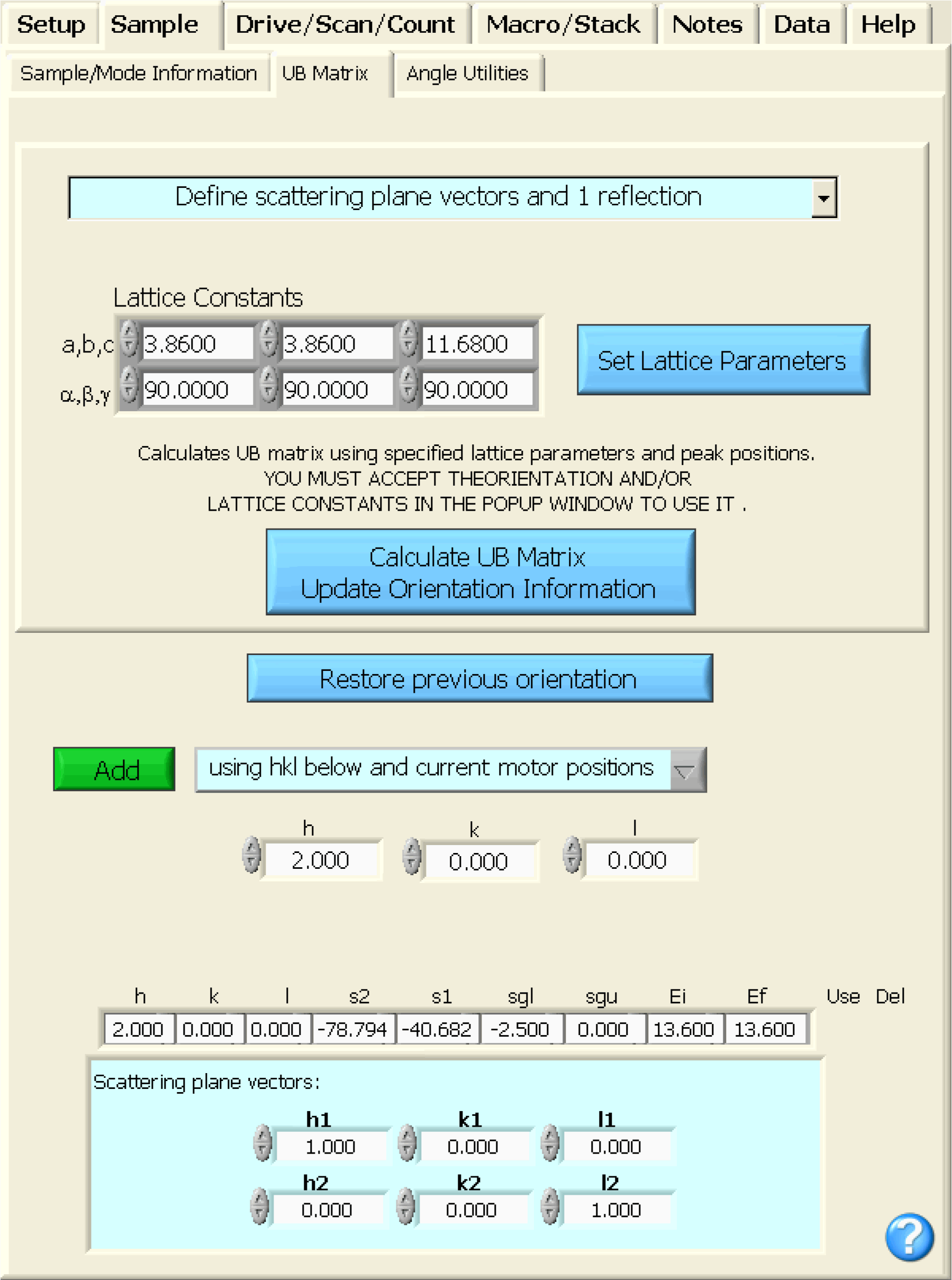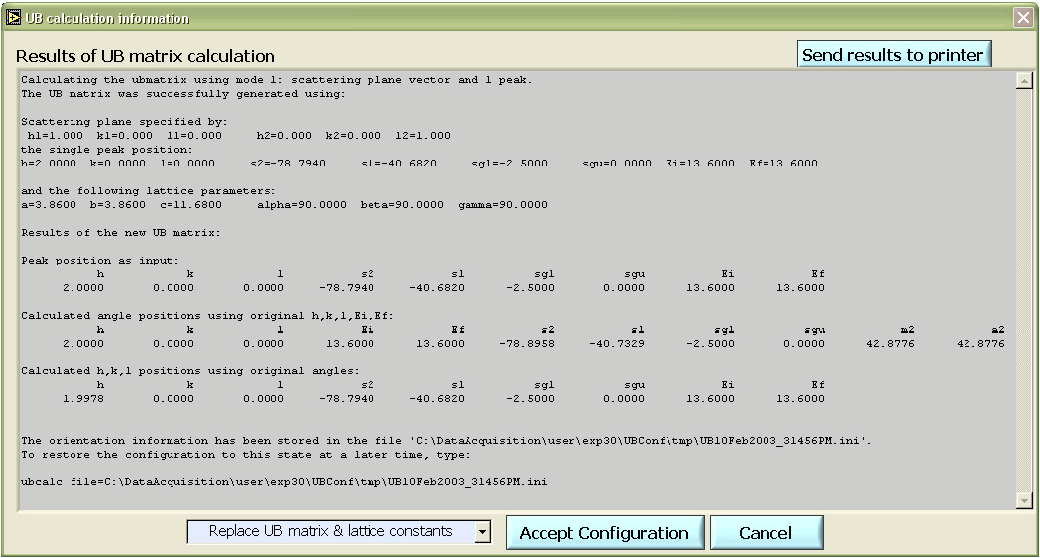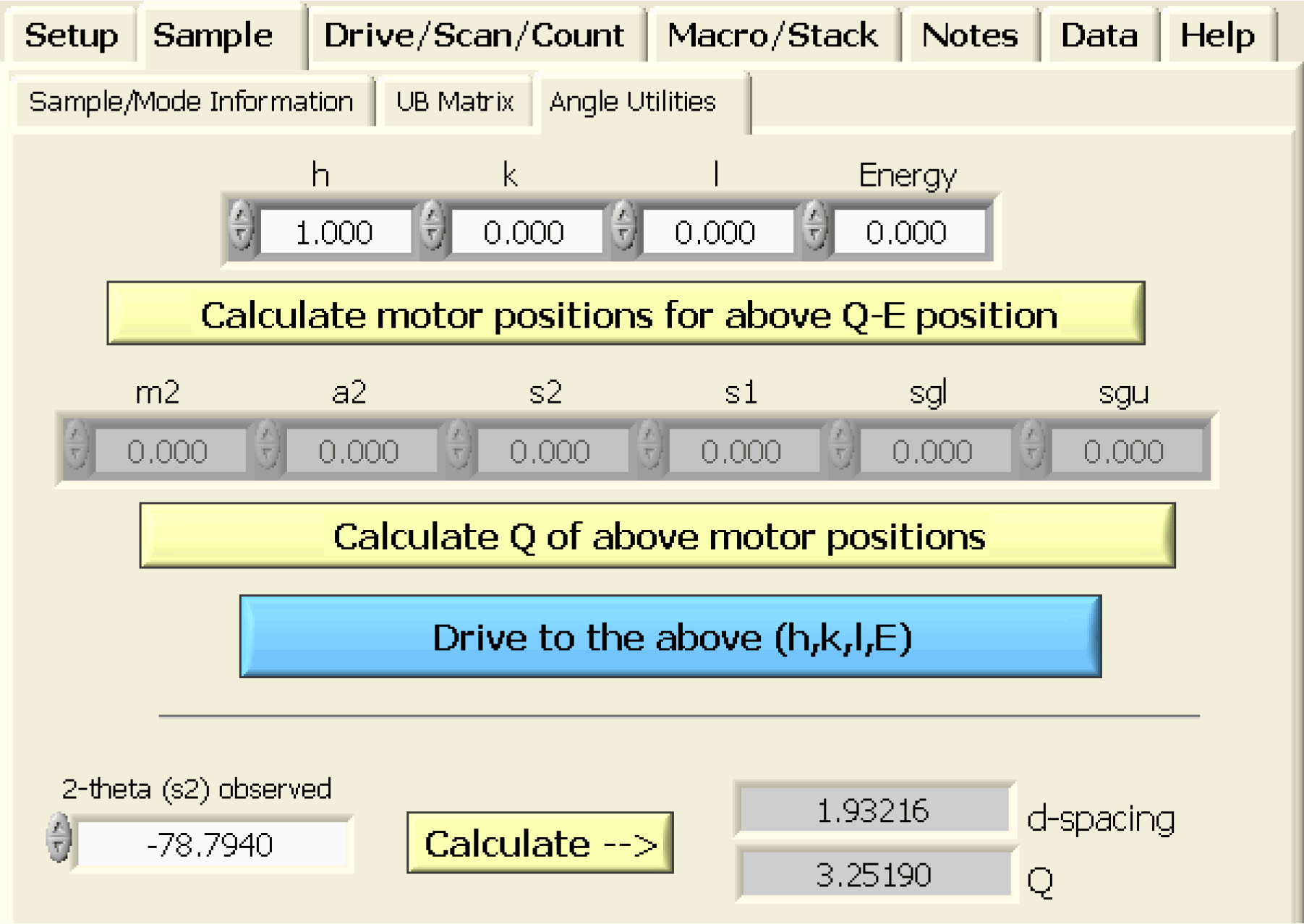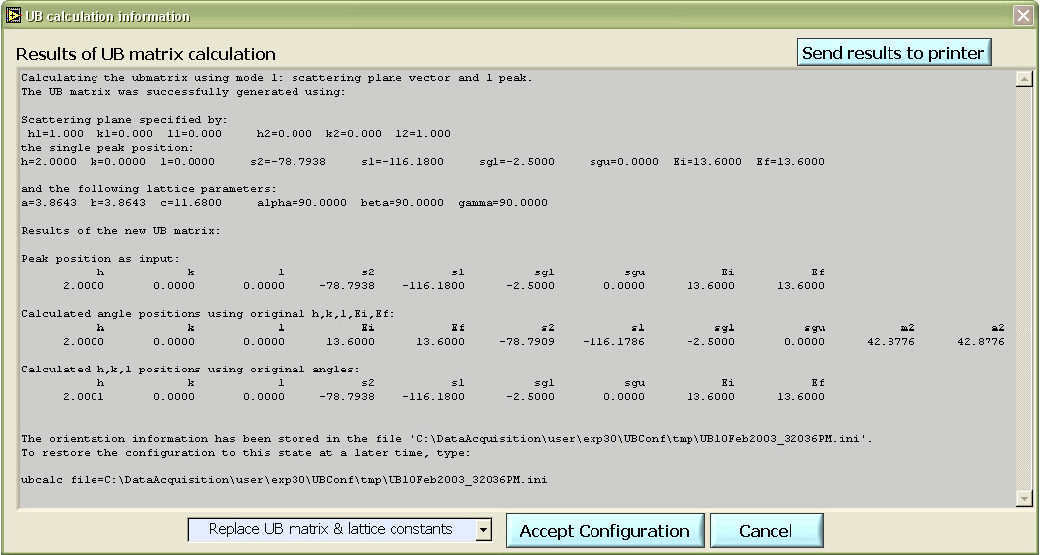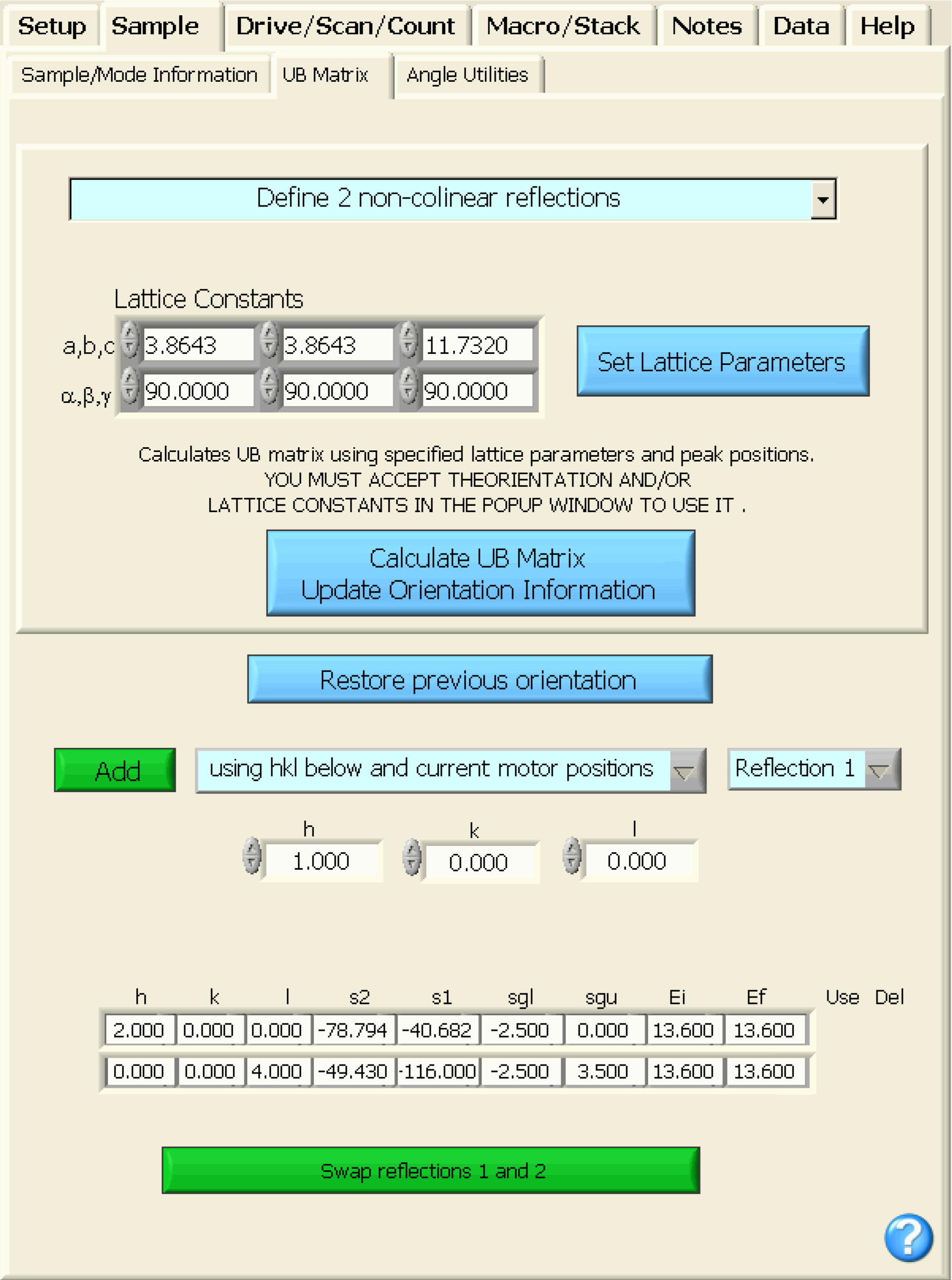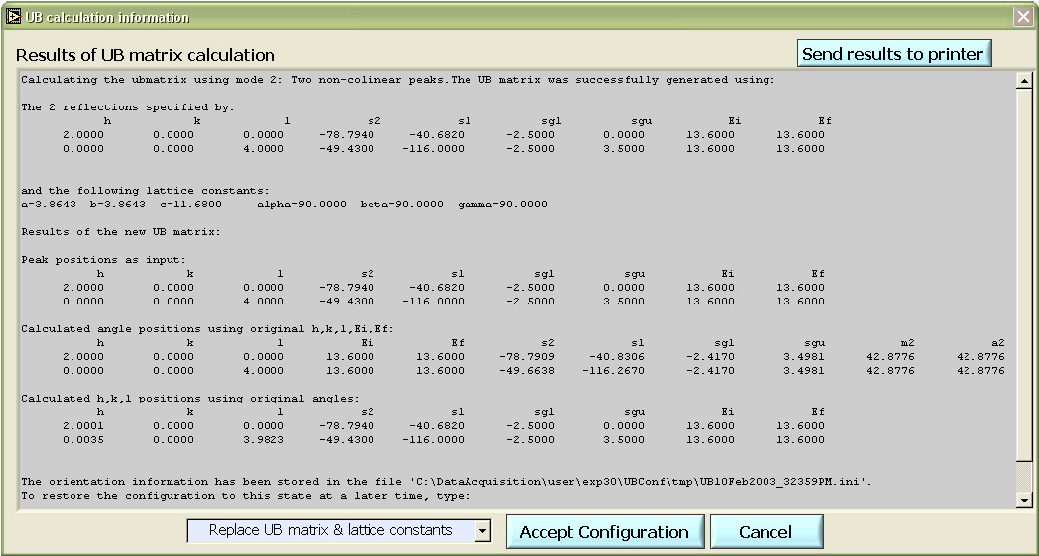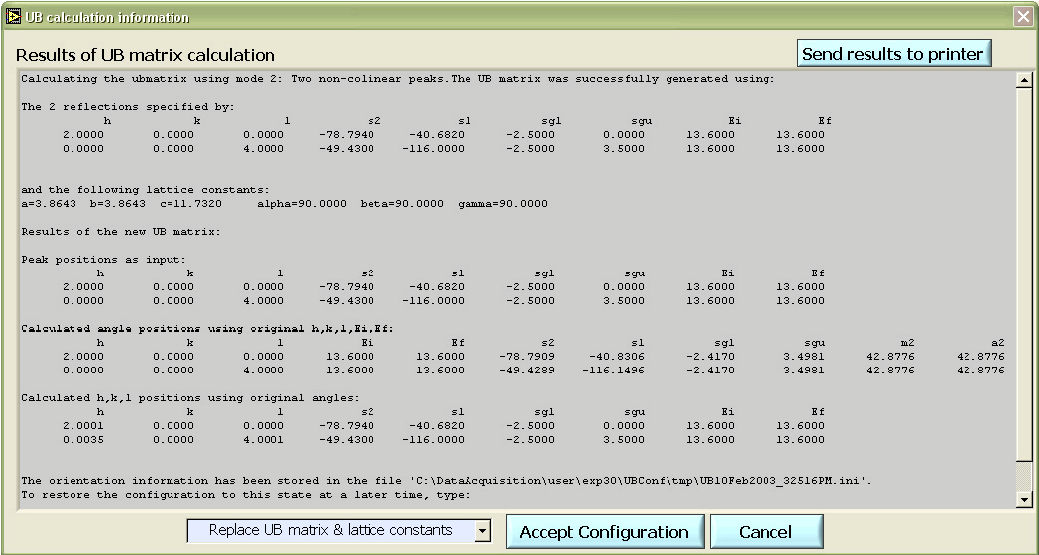SPICE
Spectrometer Instrument Control Environment
PONTAトップページ
SPICE html manualトップページ
軸立て方法
★ SPICEでは角度から逆格子空間への変換はUB-Matrixを用いてなされる為、軸立て方法は通常3軸分光器で行われる方法と少し異なります。
★ UB Matrixは通常4軸分光器に用いられていますが、SPICEでは標準3軸分光器で機能するように修正されています。 (標準3軸分光器で通常2つの直交したアークとサンプル回転角 によってサンプルの向きを定義しています。それに加えて、非弾性散乱スキャンが可能になっています。 この方式の利点は 以下の2点です。
- arc(サンプルゴニオティルト)により、逆格子空間上を動くことができる。
- 全ての対称性(trinicを含む)をプログラムで取り扱える。
★ しかし、SPICEでは4軸回折装置で用いられているようなUB matrixの決定方法の様にピークを多数スキャンして結晶の晶系と関係なく最小二乗法で観測値に合うようにUB matrixを決めるのではなく、格子パラメタは変えません。
★ その最たる例は格子定数です。格子定数は観測した2thetaの角度からGUIを用いて"ユーザー"が計算し、その値を"ユーザー"が入力します。
★ また、alpha=beta=gamma=90degreeの時、直交すべきa*軸、b*軸の間の角度が90.3°と観測された場合、alpha,beta,gammaを90°のままにしておくと、b*軸の反射にbrコマンド等で移動すると0.3°ωがピーク位置からずれます。これはFILMANの時と同様です。
★ もし、計算結果をピーク位置に合わせたい時には、alpha,beta,gammaを適宜変えてください。
1つ目のピークによるUB matrixの決定
第1反射の定義
★
大まかな軸立ての情報は、新しい実験を始める為に beginコマンドが実行されたとき入力します。例として(h0l)散乱面上のYBCO結晶の場合の例を下図に示します。
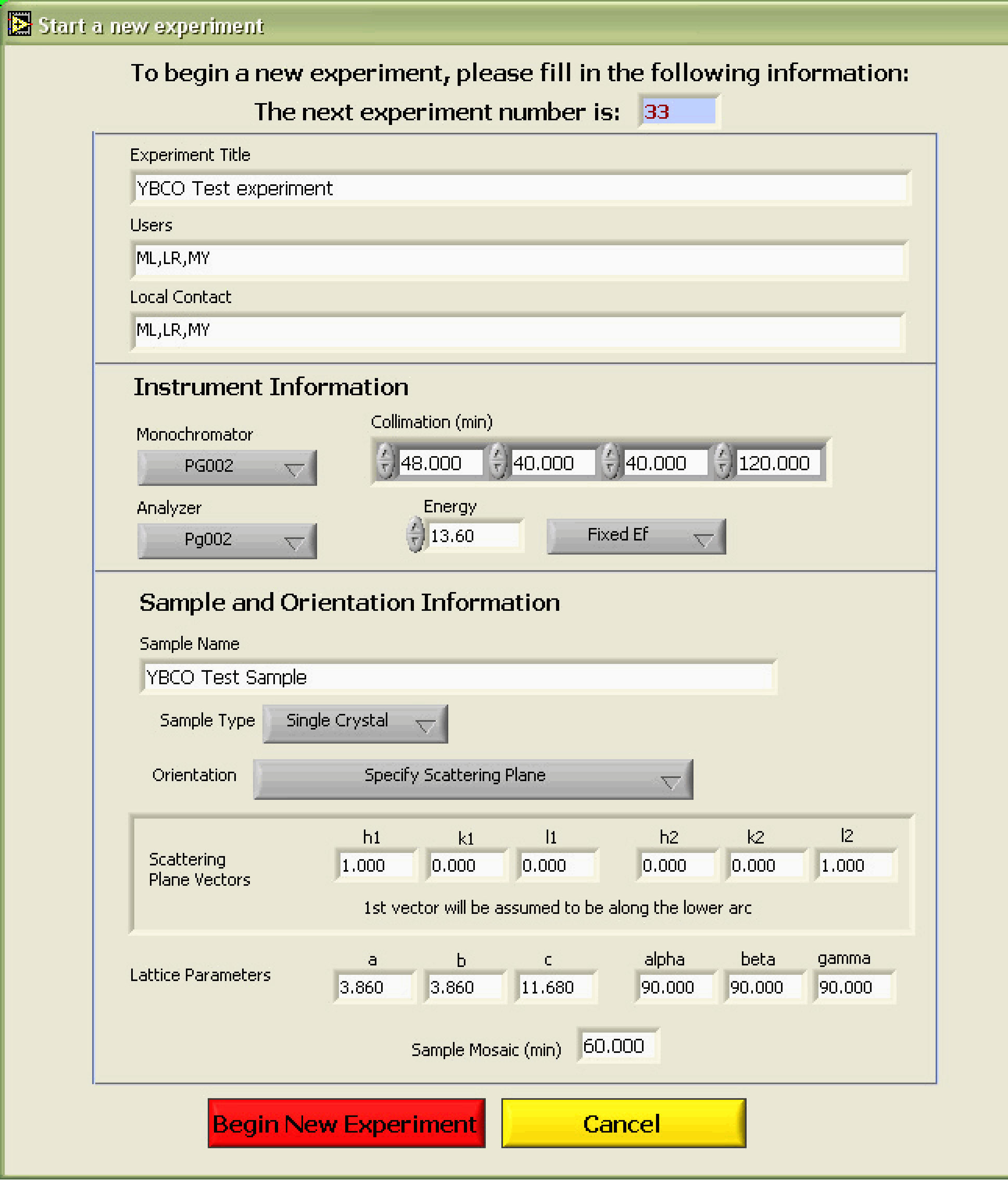 ★
Specify Scattering Planeオプションが選択されている場合、
散乱面を決めるベクトルの2つの反射の(h,k,l)指標と
格子定数を与えなければなりません。
★
Specify Scattering Planeオプションが選択されている場合、
散乱面を決めるベクトルの2つの反射の(h,k,l)指標と
格子定数を与えなければなりません。
★
モノクロメーターとアナライザーが弾性散乱の位置にあることを確認します。
★
UB-Matirxの初期状態をチェックする為に、
SampleタブーUB Matrixタブを選びます。Beginボックスが
上図のように入力されたら、UB Matrixタブは、
Define scattering plane vectors and 1 reflection
(1つの反射で散乱面を定義)モードに設定されている
はずです。格子定数と散乱面を張るベクトルがBeginボックスと
同じに設定され、第1反射が自動的に設定されています。
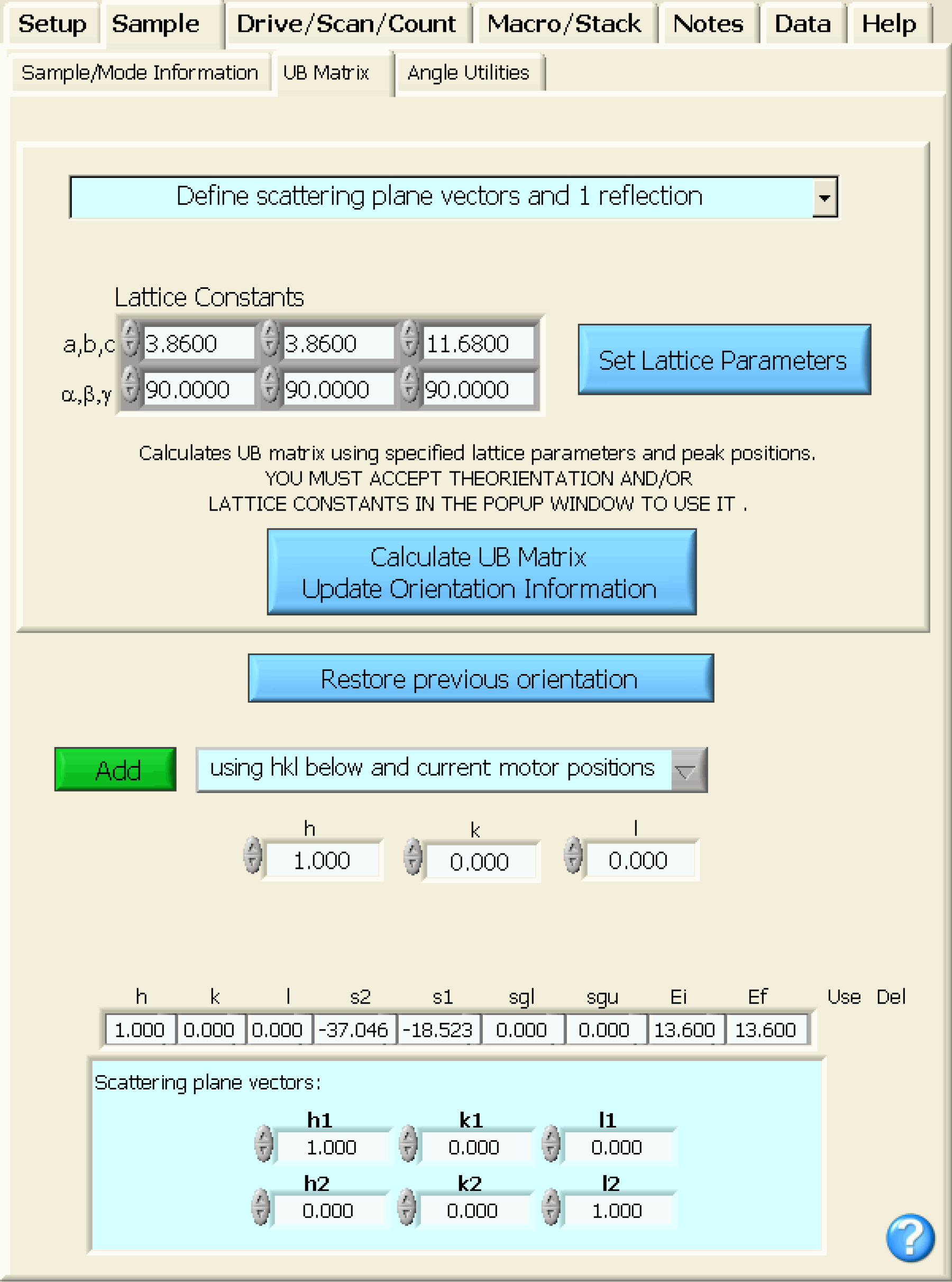 ★
第1ベクトルに平行な既知の反射位置に分光器を動かします。
(例えば上図の例では(2,0,0)反射に動かします。)
★
第1ベクトルに平行な既知の反射位置に分光器を動かします。
(例えば上図の例では(2,0,0)反射に動かします。)
- drive h 2 k 0 l 0
- br 2 0 0
- brはブラッグ反射位置に動かすエイリアスです。上記のdriveコマンドと同じ命令を与えます。
★
サンプルを載せ第1ベクトルのbisecting方向に向けます。例では
試料の[100]軸を向けます。
★
ピークの反射強度が最大になるようにa2、c2、RXを最適化します。
ピークのoptimize
★ 例としてピークがa2=-79、c2=-40にあるとします。プラスマイナス1°、ステップ0.1°のωスキャンは以下の様になります。
★ もし現在角を中心にプラスマイナス1°、ステップ0.1°のωスキャンを行いたい場合は以下のコマンドでも同じスキャンが行われます。
★ しかもcenterコマンドではスキャン後にピークの重心角度に自動的に移動してくれます。
★ ωがoptimizeされたら、そのc2でθ-2θスキャンを行う時は
と入力すると現在角を中心にa2をプラスマイナス1°、ステップ0.1°、c2をプラスマイナス0.5°、ステップ0.05°のスキャンが行われます。th2thコマンドはスキャン後に自動でピーク位置に移動しないのでfitting等を行い、ピーク角度にdriveもしくはmvで移動してください。
格子定数の再設定
★ FILMANではnaと入力すれば格子定数パラメータが変更されましたが、SPICEではGUIを使いユーザーが計算してその値を入力します。ここで、以下の角度で反射強度が最大値を取ると仮定します。
- A2=-78.94
- C2=-40.682
- RX=-2.5
★
分光器の角度が上記の値になっていると仮定します。
UB Matrixタブに観測した反射の指数を入れます。h=2,k=0,l=0,
そして緑のAddボタンを押します。これにより下図のようになります。
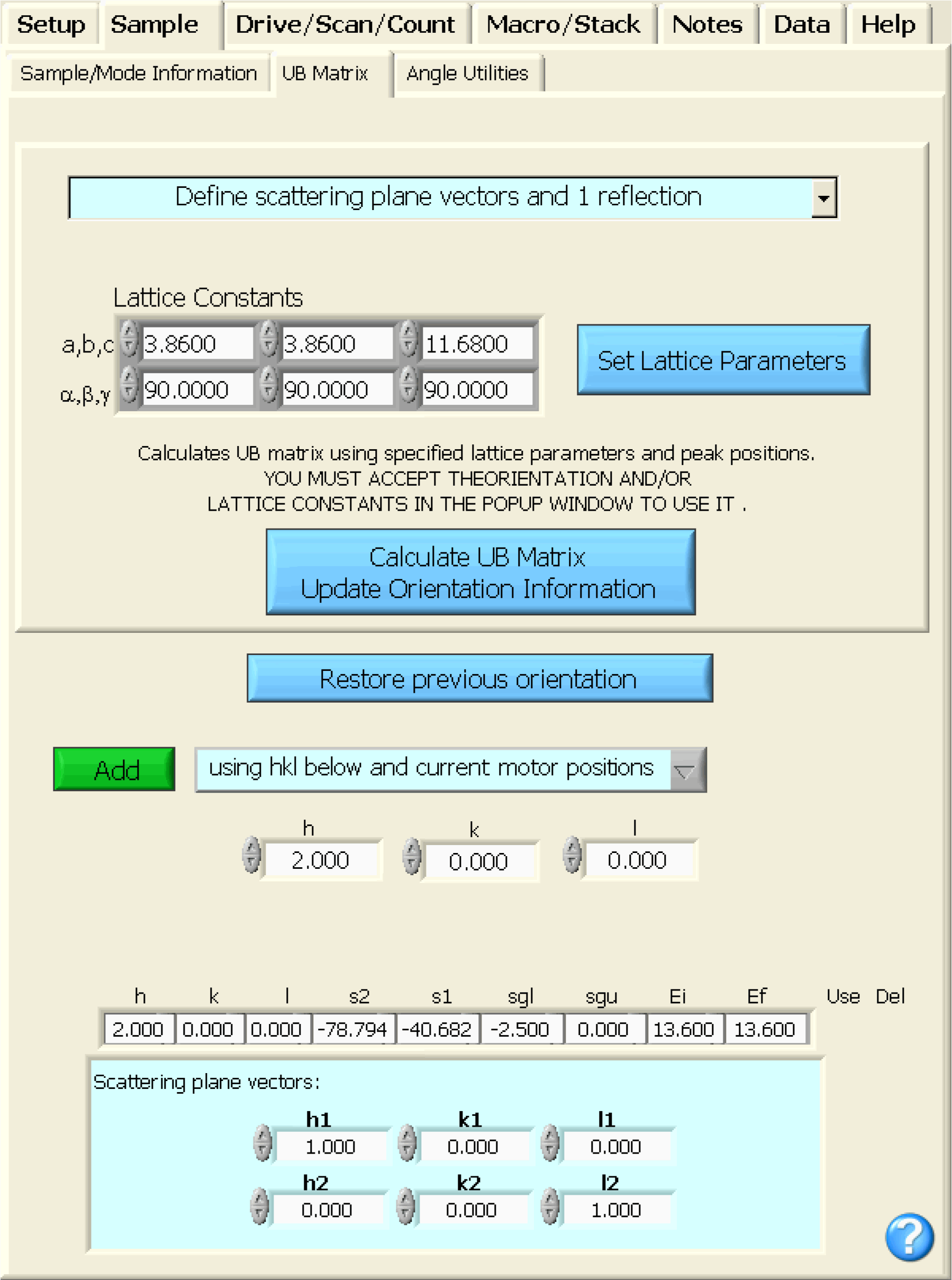 ★ 入力したピーク位置を用いてUB Matrixを計算するには、青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンをクリックします。するとUB Matrixの計算結果が書かれたボックスが現れます。この中に、UB Matrixタブで入力したピーク情報、入力した(h,k,l)反射の計算角度、モーターの角度から計算した(h,k,l)指数の情報を見ることができます。
★ 入力したピーク位置を用いてUB Matrixを計算するには、青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンをクリックします。するとUB Matrixの計算結果が書かれたボックスが現れます。この中に、UB Matrixタブで入力したピーク情報、入力した(h,k,l)反射の計算角度、モーターの角度から計算した(h,k,l)指数の情報を見ることができます。
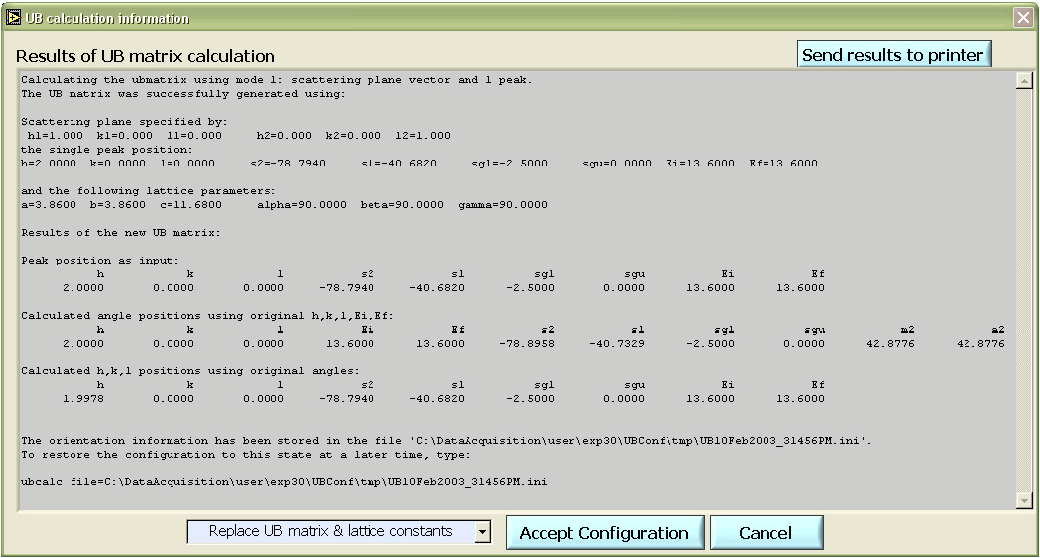 ★
計算された指数hが2ではないことが分かります。これは入力した格子定数が妥当な値ではないからです。この時点で、青いAccept Configurationボタンをクリックして、このUB Matrixを認めるか、もしくはキャンセルして格子定数を微調整することができます。この例では、キャンセルする場合を選ぶことにします。
★
計算された指数hが2ではないことが分かります。これは入力した格子定数が妥当な値ではないからです。この時点で、青いAccept Configurationボタンをクリックして、このUB Matrixを認めるか、もしくはキャンセルして格子定数を微調整することができます。この例では、キャンセルする場合を選ぶことにします。
★
SPICEには多くの角度計算ユーティリティーがあります(コマンドラインからcalcでも計算できます。)ユーティリティーの1つは、散乱角A2からd-spacingを計算する事が出来ます。下にその画面を示します。
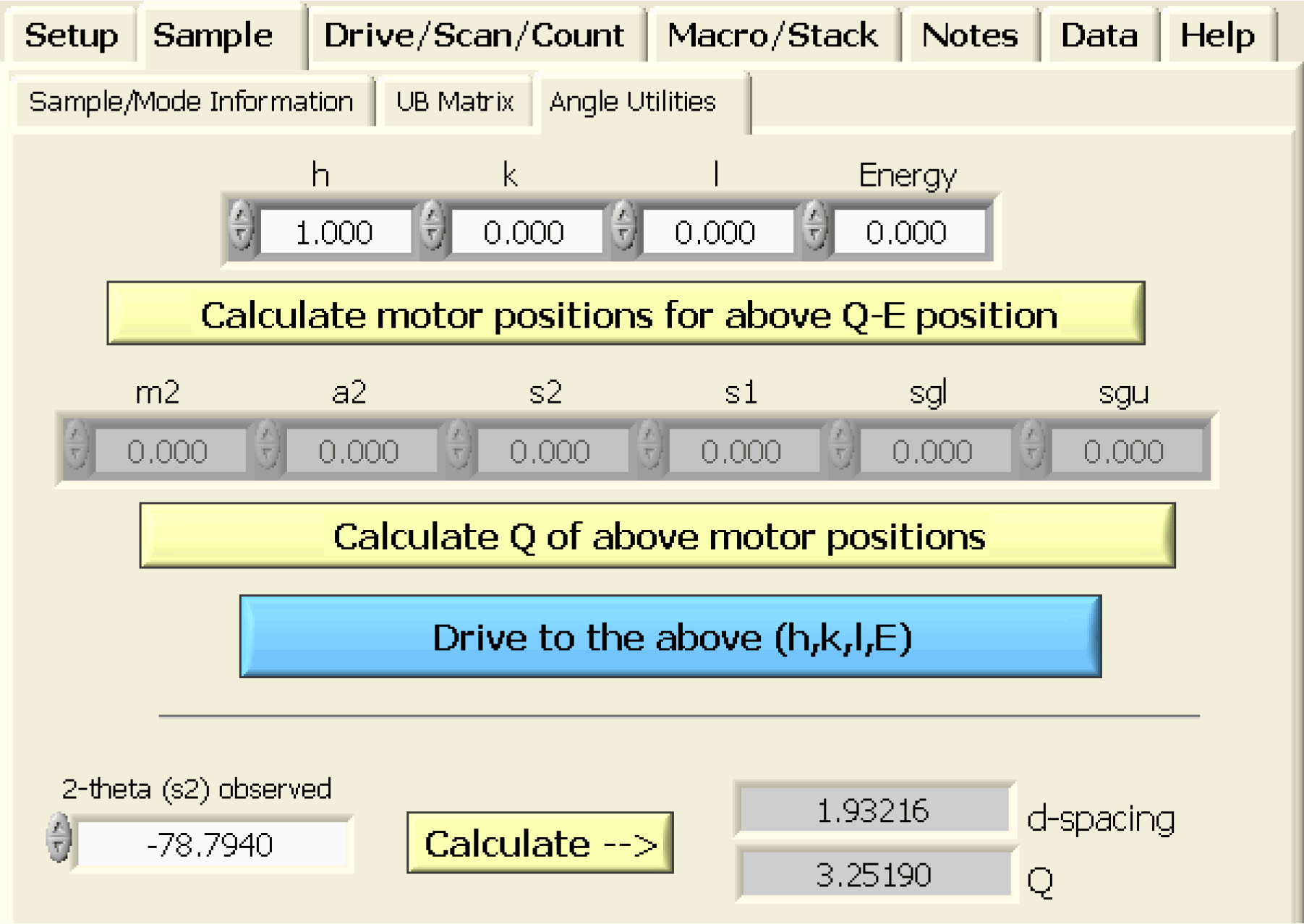 ★
上図の計算から、d-spacing 1.93216は格子定数2*1.93216=3.86432を得る事ができます。この値をUB Matrixタブの格子定数に入力して青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンを押します。すると、下のボックスが現れます。
★
上図の計算から、d-spacing 1.93216は格子定数2*1.93216=3.86432を得る事ができます。この値をUB Matrixタブの格子定数に入力して青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンを押します。すると、下のボックスが現れます。
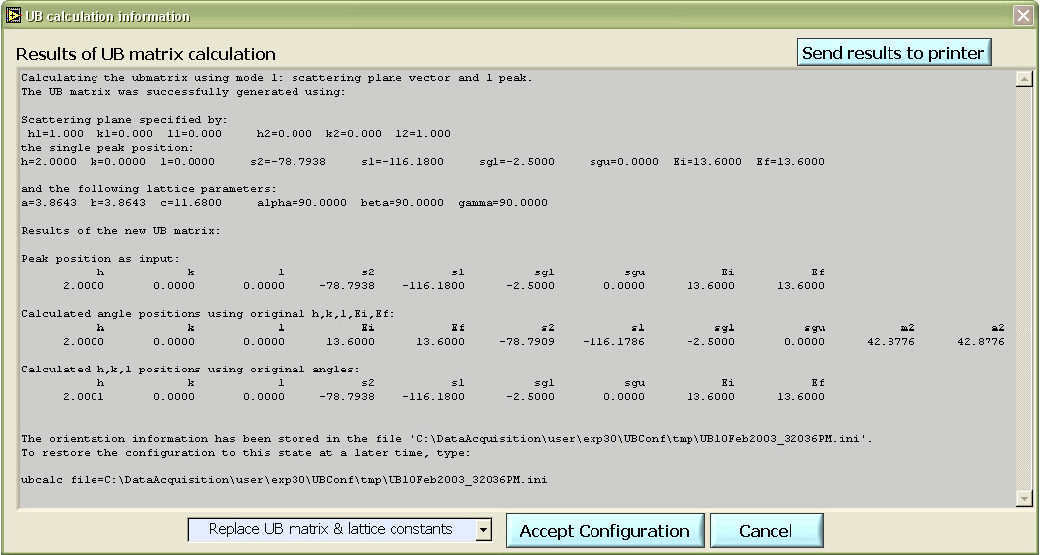 ★
入力した格子定数は観測された散乱角A2と合うことが分かりましたので、Accept Configurationボタンをクリックして現在のUB Matrixを認めます。
★
入力した格子定数は観測された散乱角A2と合うことが分かりましたので、Accept Configurationボタンをクリックして現在のUB Matrixを認めます。
2つ目のピークによるUB matrixの決定
★ これでa軸に関して確かな軸情報が得られました。次に結晶が最初のbegin画面で入力したように(h0l)散乱面にいる事を確認します。そして、散乱面上の別の反射を探して2つのピーク位置情報からUB Matrixを再計算します。
★
散乱面を張るもうひとつのベクトルの方向は[001]方向なので、この方向の反射を探します(この例では(004)反射とします)。(200)反射のときと同様に、(004)反射位置に分光器を動かします。
- drive h 0 k 0 l 4
- もしくはbrエイリアスを使って
- br 0 0 4
★
現在、5Gでは第1反射のティルトが下側のティルトになっています。もし第1反射のティルトが大きい場合、第2反射でティルトを動かすとω成分の回転もすることになります。そのような場合は一旦、第1反射のティルトをゼロにして第2反射を最適化してください。
★
(004)反射の散乱角A2、入射角C2、ティルトRYをスキャンして(0,0,4)反射を最適化します。ここでは以下の角度で最適化したと仮定します。
- s2=-49.43
- s1=-116.0
- sgu=3.5
★
これらの情報をUB Matrixに入力します。そのためには、SampleタブーUB MatrixタブのcalculationモードをDefine scattering plane vectors and 1 reflectionからDefine 2 non-collinear reflectionsに変更する必要があります。現在角が(004)反射の最適条件にあるとします。まず、(hkl)に(004)と入力し、青いプルダウンメニューからReflection2を選び、最後に緑のAddボタンを押します。そうすると、UB Matrixタブは以下のようになります。
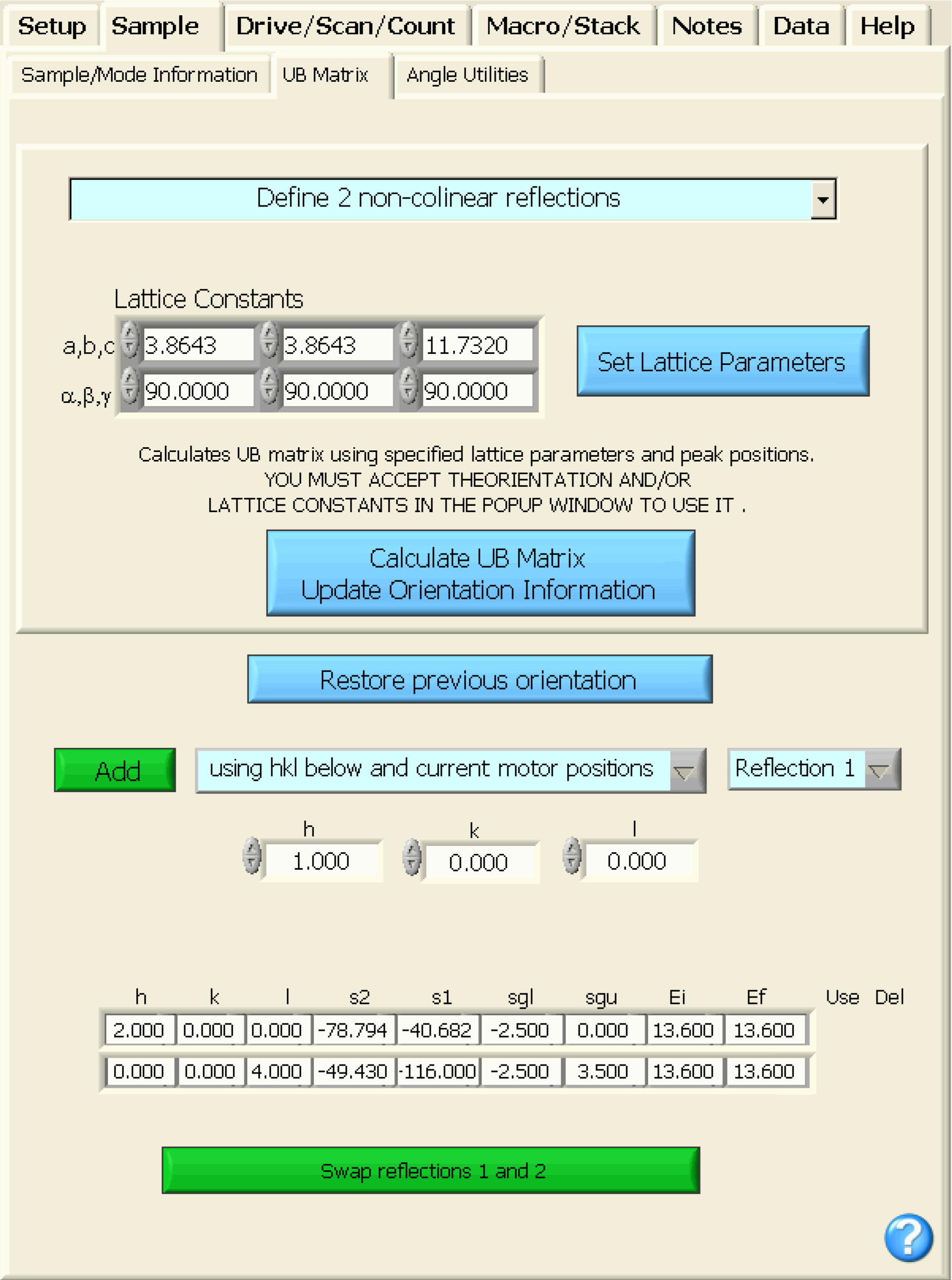 ★ (200)反射のときと同様に、Calculate UB Matrix Update OrientationボタンをクリックしてUB Matrixを計算します。下のようなボックスが現れます。
★ (200)反射のときと同様に、Calculate UB Matrix Update OrientationボタンをクリックしてUB Matrixを計算します。下のようなボックスが現れます。
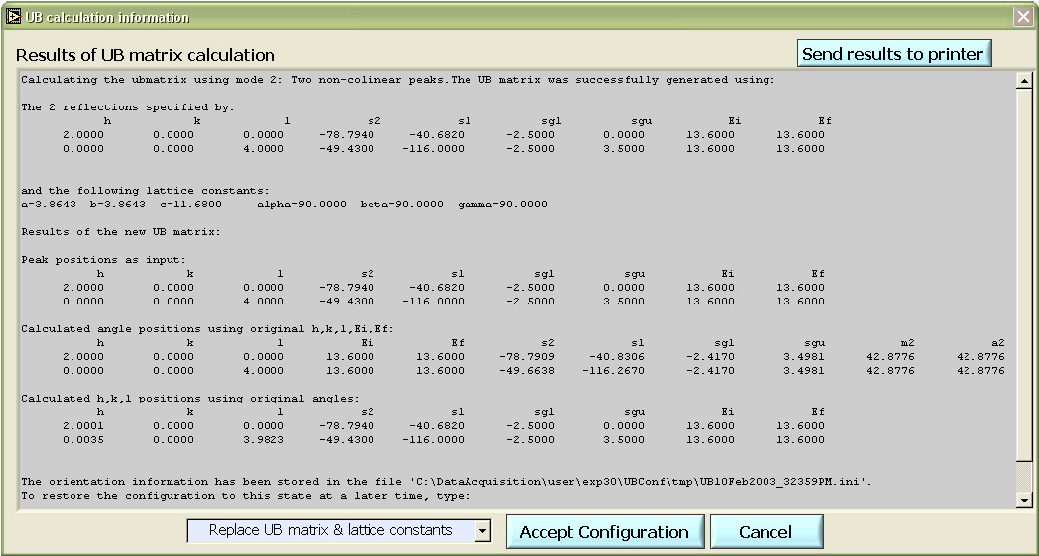 ★
上の例では、(004)反射の計算された指数lが4ではありません。これは格子定数がずれていることを示しています。(200)の時と同様に散乱角から格子定数を計算すると、c=11.68から11.732に変更しなければならない事が分かります。この新しい値を入れてUB Matrixを再計算した結果が下図です。(青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンを押します。)
★
上の例では、(004)反射の計算された指数lが4ではありません。これは格子定数がずれていることを示しています。(200)の時と同様に散乱角から格子定数を計算すると、c=11.68から11.732に変更しなければならない事が分かります。この新しい値を入れてUB Matrixを再計算した結果が下図です。(青いCalculate UB Matrix Update Orientation Informationボタンを押します。)
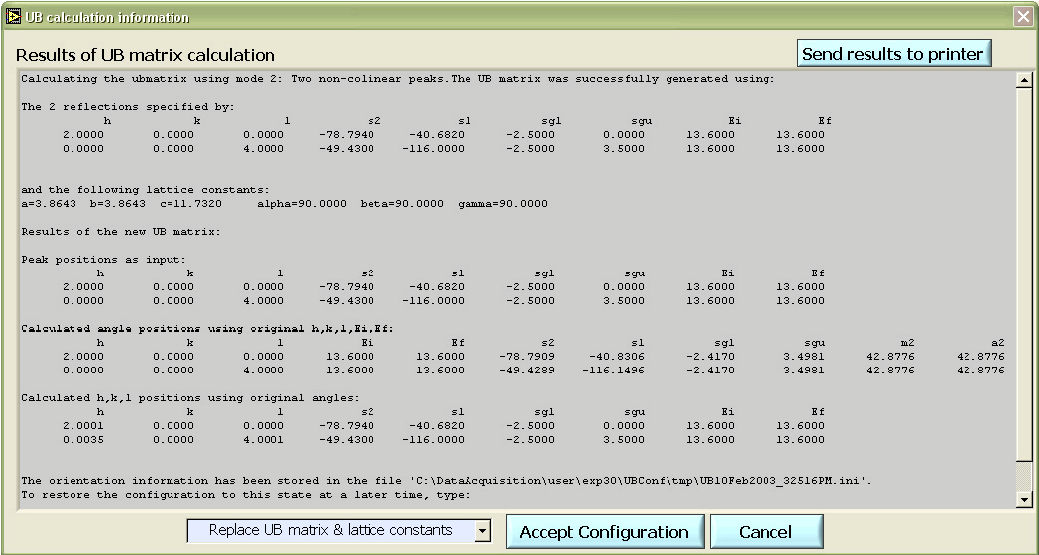 ★
これで、両方の反射の計算された指数がほぼ正しくなりました。(004)反射のずれは2つの反射が正確に90度離れていない事に起因しています。
★
これで、両方の反射の計算された指数がほぼ正しくなりました。(004)反射のずれは2つの反射が正確に90度離れていない事に起因しています。
alpha,beta,gammaの再設定
★ reflection1とreflection2の計算角ω(c2)がピーク位置とあわない場合は、alpha,beta,gammaをずらす事で合わせる事が出来ます。
★
例えばcubic結晶において、本来a軸(reflection1)とb軸(reflection2)が90°をなすべきなのが、観測されたピークのωが90.3°なしていた場合、gammaを90.3°にずらさないと、reflection2の計算位置が観測されたピーク位置からずれます。他の晶系、散乱面でもreflection2のピーク位置(ω)が計算結果とずれる場合、適宜、alpha,beta,gammaを調整してください。
★ Sample>Angle UtilitiesタブにあるCalculate angle between Q’s with above motor positionsを使うと2つのピークポジション間の角を計算できます。
confファイル
★LogにUB matrixのconfファイルの名前が出力されています。画面中央の濃い青いボタンRestore previous orientationを押し、conf ファイルを選べばいつでもそのUB matrixの状態に戻ることが出来ます。
Edited by Matsuura; Updated 2007-05-05;
コメント、質問はこちらへ